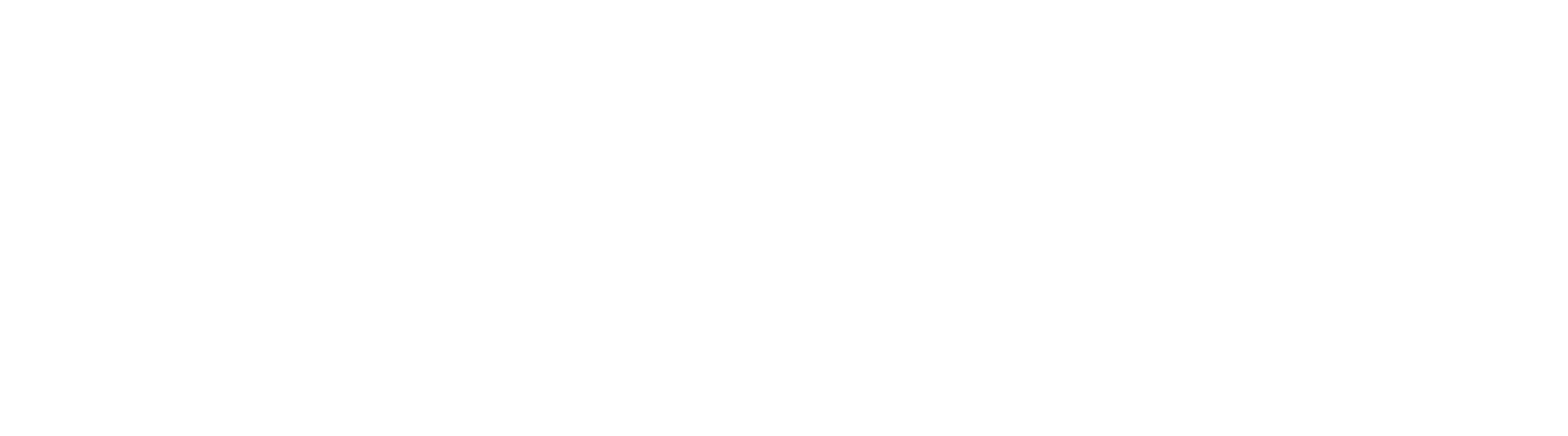GRAND SUMO TOURNAMENT 2026
日本の偉大な国技・大相撲
| ◆日本の国技である相撲。その競技者である力士はただの太った人ではない。 脂肪の下には鍛え抜かれた素晴らしい筋肉。そしてこの大きな体格ながら素晴らしい柔軟性を持ち、脚は木の幹のようなたくましさ。その身体能力はまさにアクロバティックで、力士は戦うための身体を持つ究極のアスリートだ。 そのぶつかり合いをぜひその目で確かめてもらいたい! |
|---|
16,000円~18,000円
おすすめポイント

チケットは観戦当日現地でお渡し
観戦チケットは観戦当日に会場でお渡ししますので、郵送の受け取りが出来ない旅行中でも予約が出来ます!

お土産にも最適!楽しい相撲グッズ付
相撲タオルと当日のお楽しみ、秘密の相撲グッズをプレゼント!

入手困難のチケットを確保!
大人気の大相撲の観戦チケットを大量に確保!日本の旅行会社だから出来る仕入れの強さ。
大相撲観戦 開催月から選択する
販売終了
【マスC席】1月東京場所 大相撲観戦チケット+楽しい相撲グッズ付
【含まれるもの】相撲観戦チケット 相撲グッズ
21,000~23,000円
販売終了
【イスC席】1月東京場所 大相撲観戦チケット+楽しい相撲グッズ付
【含まれるもの】相撲観戦チケット 相撲グッズ
16,000円
販売終了
【イスB席】1月東京場所 大相撲観戦チケット+楽しい相撲グッズ付
【含まれるもの】相撲観戦チケット 相撲グッズ
18,000円
販売終了
1月場所日程表
アクセス
地図
JR総武線 両国駅西口下車 徒歩2分
JR総武線両国駅の西口を出てすぐ右に曲がります。すぐに正面に「両国駅広小路」があり、向かって左手の「両国駅広小路」を抜けた右手に「両国国技館」の入り口があります。
都営地下鉄大江戸線 両国駅下車 徒歩5分
大江戸線両国駅の「A3出口」を出たあと清澄通を左へ進みます。山岡商店の手前を左折します。アパホテルのあるT字路に差し掛かったら左折します。そのまま進むと国技館通りへ出るので、左へ曲がった先が両国国技館になります。
【イスA席】3月大阪場所 大相撲観戦ツアー イスA席チケット+楽しい相撲グッズ付
【含まれるもの】相撲観戦チケット 相撲グッズ
18,000円
【イスD席】3月大阪場所 大相撲観戦 イスD席チケット+楽しい相撲グッズ付
【含まれるもの】相撲観戦チケット 相撲グッズ
14,000円~14,500円
3月場所日程表
アクセス
地図
地下鉄各線なんば駅5番出口から徒歩約5分
南海なんば駅南出口から徒歩約5分
大相撲5月場所は現在販売期間外です
五月場所日程表
アクセス
地図
JR総武線 両国駅西口下車 徒歩2分
JR総武線両国駅の西口を出てすぐ右に曲がります。すぐに正面に「両国駅広小路」があり、向かって左手の「両国駅広小路」を抜けた右手に「両国国技館」の入り口があります。
都営地下鉄大江戸線 両国駅下車 徒歩5分
大江戸線両国駅の「A3出口」を出たあと清澄通を左へ進みます。山岡商店の手前を左折します。アパホテルのあるT字路に差し掛かったら左折します。そのまま進むと国技館通りへ出るので、左へ曲がった先が両国国技館になります。
大相撲7月場所は現在販売期間外です
七月場所日程表
アクセス
地図
名古屋市営地下鉄名城線 『名城公園駅』から徒歩約1分
大相撲9月場所は現在販売期間外です
九月場所日程表
アクセス
地図
JR総武線 両国駅西口下車 徒歩2分
JR総武線両国駅の西口を出てすぐ右に曲がります。すぐに正面に「両国駅広小路」があり、向かって左手の「両国駅広小路」を抜けた右手に「両国国技館」の入り口があります。
都営地下鉄大江戸線 両国駅下車 徒歩5分
大江戸線両国駅の「A3出口」を出たあと清澄通を左へ進みます。山岡商店の手前を左折します。アパホテルのあるT字路に差し掛かったら左折します。そのまま進むと国技館通りへ出るので、左へ曲がった先が両国国技館になります。
販売終了
販売終了
販売終了
【イスA席】11月九州場所 大相撲観戦チケット+打ち上げパーティー
【含まれるもの】相撲観戦チケット パーティーでの料理・ドリンク
30,000円
十一月場所日程表
アクセス
地図
電車でお越しのお客様
・地下鉄「呉服駅」より徒歩約12分
バスでお越しのお客様
・博多駅(博多口)→博多駅西日本シティ銀行前Fのりば〈99番〉約11分→国際センターサンパレス前下車、徒歩すぐ
・博多駅(博多口)→博多駅西日本シティ銀行前Fのりば〈88番・BRT〉約11分→国際会議場サンパレス前下車、徒歩すぐ